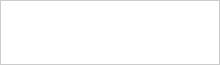道路土工
【材料】
| 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 |
|---|---|---|---|---|
| 必須 | 土の締固め 試験 |
JIS A 1210 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時(材料が岩砕の場合は除く)。 但し、法面、路肩部の土量は除く。 |
| CBR試験(路床) | JIS A 1211 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 (材料が岩砕の場合は除く) |
|
| その他 | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 |
| 土粒子の 密度試験 |
JIS A 1202 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 | |
| 土の含水比 試験 |
JIS A 1203 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 | |
| 土の液性限界 塑性限界試験 |
JIS A 1205 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 | |
| 土の 一軸圧縮試験 |
JIS A 1216 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 | |
| 土の 三軸圧縮試験 |
地盤材料試験の方法と解説 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 | |
| 土の 圧密試験 |
JIS A 1217 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 | |
| 土の せん断試験 |
地盤材料試験の方法と解説 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 | |
| 土の 透水試験 |
JIS A 1218 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 |
【施工】
| 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必須 | 現場密度の 測定 ※右記試験方法 (3種類)のいずれか を実施する |
最大粒径≦53mm:砂置換法(JIS A 1214) 最大粒径>53mm:舗装調査・試験法便欄[4]-256 突砂法 |
【砂質土】 ・路体:次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の90%以上(締固め試験(JIS A 1210)A・B法) ・路床及び構造物取付け部:次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の95%以上(締固め試験(JIS A 1210)A・B法)もしくは90%以上(締固め試験(JIS A 1210)C・D・E法) 【粘性土】 ・路体:自然含水比またはトラフィカビリティが確保できる含水比において、空気間隙率Vaが2%≦Va≦10%または飽和度Srが85%≦Sr≦95%。 ・路床及び構造物取付け部:トラフィカビリティが確保できる含水比において、空気間隙率Vaが2%≦Va≦8% ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準を適用することができる。 その他、設計図書による。 |
路体の場合、1,000m³につき1回の割合で行う。 但し、3,000m³未満の工事は、1工事あたり3回以上。 路床及び構造物取付け部の場合、500m³につき1回の割合で行う。但し、1,500m³未満の工事は1工事当たり3回以上。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。 |
|||||||
| または、「R1計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)」 | 【砂質土】 ・路体:次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度の92%以上(締固め試験(JIS A 1210)A・B法)。 ・路床及び構造物取付け部:次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度の97%以上(締固め試験(JIS A 1210)C・D・E法)。 【粘性土】 ・路体、路床及び構造物取付け部:自然含水比またはトラフィカビリティが確保できる含水比において、1管理単位の現場空気間隙率の平均値が8%以下。 ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準を適用することができる。 または、設計図書による。 |
盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位ごとに管理を行うものとする。 路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m²を標準とし、1日の施工面積が2,000m²以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。
|
・最大粒径<100mmの場合に適用する。 左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、再転圧を行うものとする。 |
||||||||
| または、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」 | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。 | 1.盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2.1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 3.土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。 |
|||||||||
| プルー フローリング |
舗装調査・試験法便覧 G023 [4]-288 |
路床仕上げ後全幅、全区間について実施する。但し、現道打換工事、仮設用道路維持工事は除く。 | ・荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。 | ||||||||
| その他 | 平板載荷 試験 |
JIS A 1215 | 各車線ごとに延長40mについて1箇所の割で行う。 | ・セメントコンクリートの路盤に適用する。 | |||||||
| 現場CBR 試験 |
JIS A 1222 | 設計図書による | 各車線ごとに延長40mについて1回の割で行う。 | ||||||||
| 含水比 試験 |
JIS A 1203 | 設計図書による | 路体の場合、1,000m³につき1回の割合で行う。ただし、5,000m³未満の工事は、1工事当たり3回以上。 路床の場合、500m³につき1回の割合で行う。ただし、1,500m³未満の工事は1工事当たり3回以上。 |
||||||||
| コーン指数の 測定 |
舗装調査・試験法便覧 S 044 [1]-273 |
設計図書による | 必要に応じて実施。 (例)トラフィカビリティが悪い時 |
||||||||
| たわみ量 | 舗装調査・試験法便覧 S 046 [1]-284 (ベンゲルマンビーム) |
設計図書による | プルーフローリングでの不良箇所について実施 |
河川・海岸土工
【材料】
| 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 |
|---|---|---|---|---|
| 必須 | 土の 締固め試験 |
JIS A 1210 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 |
| その他 | 土の 粒度試験 |
JIS A 1204 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 |
| 土粒子の 密度試験 |
JIS A 1202 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 | |
| 土の 含水比試験 |
JIS A 1203 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 | |
| 土の 液性限界 塑性限界試験 |
JIS A 1205 | 設計図書による | 当初及び土質の変化した時。 | |
| 土の 一軸圧縮試験 |
JIS A 1216 | 設計図書による | 必要に応じて。 | |
| 土の 三軸圧縮試験 |
地盤材料試験の方法と解説 | 設計図書による | 必要に応じて。 | |
| 土の 圧密試験 |
JIS A 1217 | 設計図書による | 必要に応じて。 | |
| 土の せん断試験 |
地盤材料試験の方法と解説 | 設計図書による | 必要に応じて。 | |
| 土の 透水試験 |
JIS A 1218 | 設計図書による | 必要に応じて。 |
【施工】
| 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必須 | 現場密度の 測定 ※右記試験方法 (3種類)のいずれか を実施する |
最大粒径≦53mm:砂置換法(JIS A 1214) 最大粒径>53mm:舗装調査・試験法便覧[4]-256 突砂法 |
【河川土工】 最大乾燥密度の90%以上。ただし、上記により難い場合は、飽和度または空気間隙率の規定によることができる。 【砂質土(25%≦75μmふるい通過分<50%)】 空気間隙率VaがVa≦15% 【粘性土(50%≦75μmふるい通過分)】 飽和度Srが85%≦Sr≦95%または空気間隙率Vaが2%≦Va≦10% または、設計図書による。 【海岸土工】 最大乾燥密度の85%以上。または、設計図書に示された値。 |
築堤は、1,000m³に1回の割合、または提体延長20mに3回の割合の内、測定頻度の高いほうで実施する。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の平均値で判定を行う。 |
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | ||||||
| または、「R1計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)」 | 【河川土工】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の92%以上。 ただし、上記により難い場合は、飽和度または空気間隙率の規定によることができる。 【砂質土(25%≦75μmふるい通過分<50%)】 空気間隙率VaがVa≦15% 【粘性土(50%≦75μmふるい通過分)】 飽和度Srが85%≦Sr≦95%または空気間隙率Vaが2%≦Va≦10% または設計図書による 【海岸土工】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度の92%以上。 または設計図書による |
盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位ごとに管理を行うものとする。 築堤は、1日1層当たりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m²を標準とし、1日の施工面積が2,000m²以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。
|
・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、再転圧を行うものとする。 |
||||||||
| または、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による。 | 施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。ただし、路肩から1m以内と締固め機械が近寄れない構造物周辺は除く。 | 1.盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2.1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 3.土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。 |
|||||||||
| その他 | 土の 含水比試験 |
JIS A 1203 | 設計図書による | 含水比の変化が認められたとき。 | 確認試験である。 | ||||||
| コーン指数の 測定 |
舗装調査・試験法便覧 S 004 [1]-273 |
設計図書による | トラフィカビリティが悪いとき。 | 確認試験である。 |
下層路盤工
【材料】
| 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績 表等によ る確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必須 | 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧 E 001 [4]-68 |
粒状路盤:修正CBR20%以上(クラッシャラン鉄鋼スラグは修正CBR30%以上) アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用いる場合で、上層路盤、基層、表層の合計厚が40cmより小さい場合は30%以上とする。 |
・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事:施工前 |
・中規模以上の工事とは、舗装施工面積が2,000m²以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 ・小規模工事とは、舗装施工面積が2,000m²未満あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満の場合が該当する。 |
○ |
| 骨材の ふるい分け試験 |
JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 |
・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事:施工前 |
○ | ||
| 土の 液性限界 塑性限界試験 |
JIS A 1205 | 塑性指数PI:6以下 | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事:施工前 ・但し、鉄鋼スラグには適用しない。 |
○ | ||
| 鉄鋼スラグの 水浸膨張性試験 |
舗装調査・試験法便覧 E 004 [4]-80 |
1.5%以下 | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事:施工前 ・CS:クラッシャラン鉄鋼スラグに適用する。 |
○ | ||
| 道路用スラグの 呈色判定試験 |
JIS A 5015 | 呈色なし | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事:施工前 |
○ | ||
| その他 | 粗骨材の すりへり試験 |
JIS A 1121 | 再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すり減り量が50%以下とする。 | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事:施工前 ・再生クラッシャランに適用する。 |
○ |
【施工】
| 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必須 | 現場密度の 測定 |
舗装調査・試験法便覧 G 021 [4]-256 砂置換法(JIS A1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用できる |
最大乾燥密度の93%以上 X₁₀ 95%以上 X₆ 96%以上 X₃ 97%以上 歩道路盤及び路肩路盤 |
・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以上(歩道路盤及び路肩路盤を除く)を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・締固め度は、10孔の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとする。 ・10孔の測定値が得がたい場合は3孔の測定値の平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3孔のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 ・1工事当たり3,000m²を超える場合は、10,000m²以下を1ロットとし、1ロット当たり10孔で測定する。 ・3,000m²以下の場合は、1工事あたり3孔以上で測定する。※ ※施工箇所が点在する維持工事(指示票によるもの)は除く。 |
・中規模以上の工事とは、舗装施工面積が2,000m²以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 ・小規模工事とは、舗装施工面積が2,000m²未満あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満の場合が該当する。 |
| プルー フローリング |
舗装調査・試験法便覧 G 023 [4]-288 |
・中規模以上の工事:随時 ・小規模工事:随時 ・全幅、全区間について実施する。 ・歩道路盤、路肩路盤を除く |
・中規模以上の工事とは、舗装施工面積が2,000m²以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 ・小規模工事とは、舗装施工面積が2,000m²未満あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満の場合が該当する。 |
||
| その他 | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | 1,000m²につき2回の割合で行う。 | ・セメントコンクリートの路盤に適用する。 | |
| 骨材の ふるい分け試験 |
JIS A 1102 | ・中規模以上の工事:異常が認められたとき | ・中規模以上の工事とは、舗装施工面積が2,000m²以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 | ||
| 土の 液性限界 塑性限界試験 |
JIS A 1205 | 塑性指数PI:6以下 | ・中規模以上の工事:異常が認められたとき | ||
| 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による | ・中規模以上の工事:異常が認められたとき |
粒度調整・再生粒度調整路盤工
【材料】
| 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績 表等によ る確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必須 | 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法便覧 E 001 [4]-68 |
修正CBR 80%以上 アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合90%以上 40℃で行った場合80%以上 |
・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模工事:施工前 |
・中規模以上の工事とは、舗装施工面積が2,000m²以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 ・小規模工事とは、舗装施工面積が2,000m²未満あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満の場合が該当する。 |
○ |
| 鉄鋼スラグの 修正CRB試験 |
舗装調査・試験法便覧 E 001 [4]-68 |
修正CBR 80%以上 | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模工事:施工前 ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS:水硬性粒度調整スラグに適用する。 |
○ | ||
| 骨材の ふるい分け試験 |
JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 |
・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模工事:施工前 |
○ | ||
| 土の 液性限界 塑性限界試験 |
JIS A 1205 | 塑性指数PI:4以下 | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模工事:施工前 ・但し、鉄鋼スラグには適用しない。 |
○ | ||
| 鉄鋼スラグの 呈色判定試験 |
JIS A 5015 舗装調査・試験法便覧 E 002 [4]-73 |
呈色なし | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模工事:施工前 ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS:水硬性粒度調整スラグに適用する。 |
○ | ||
| 鉄鋼スラグの 水浸膨張性試験 |
舗装調査・試験法便覧 E 004 [4]-80 |
1.5%以下 | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模工事:施工前 ・水硬性粒度調整スラグに適用する。 |
○ | ||
| 鉄鋼スラグの 一軸圧縮試験 |
舗装調査・試験法便覧 E 003 [4]-75 |
1.2Mpa以上(14日) | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模工事:施工前 ・HMS:水硬性粒度調整スラグに適用する。 |
○ | ||
| 鉄鋼スラグの 単位容積質量試験 |
舗装調査・試験法便覧 A 023 [2]-131 |
1.50kg/L以上 | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模工事:施工前 ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS:水硬性粒度調整スラグに適用する。 |
○ | ||
| その他 | 粗骨材の すりへり試験 |
JIS A 1121 | 50%以下 | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模工事:施工前 ・粒度調整及びセメントコンクリート再生骨材を使用した再生粒度調整に適用する。 |
・中規模以上の工事とは、舗装施工面積が2,000m²以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 ・小規模工事とは、舗装施工面積が2,000m²未満あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満の場合が該当する。 |
○ |
| 硫酸ナトリウム による骨材の 安定性試験 |
JIS A 1122 | 20%以下 | ・中規模以上の工事:施工前、材料変更時 ・小規模工事:施工前 |
○ |
【施工】
| 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必須 | 現場密度の 測定 |
舗装調査・試験法便覧 G 021 [4]-256 砂置換法(JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用できる |
最大乾燥密度の93%以上 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上 歩道路盤及び路肩路盤 |
・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以上(歩道路盤及び路肩路盤を除く)を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・締固め度は、10孔の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとする。 ・10孔の測定値が得がたい場合は3孔の測定値の平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3孔のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 ・1工事当たり3,000m²を超える場合は、10,000m²以下を1ロットとし、1ロット当たり10孔で測定する。 ・3,000m²以下の場合は、1工事あたり3孔以上で測定する。※ ※施工箇所が点在する維持工事(指示票によるもの)は除く。 |
・中規模以上の工事とは、舗装施工面積が2,000m²以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上の場合が該当する。 ・小規模工事とは、舗装施工面積が2,000m²未満あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満の場合が該当する。 |
| 粒度 (2.36mmフルイ) |
舗装調査・試験法便覧 A 003 [2]-16 |
2.36mmふるい:±15%以内 | ・中規模以上の工事:定期的または随時(1回~2回/日) | ||
| 粒度 (75μmフルイ) |
75μmふるい:±6%以内 | ・中規模以上の工事:異常が認められたとき。 | |||
| 含水比試験 | 舗装調査・試験法便覧 F 003 [4]-93 迅速試験方法によることができる |
-(最適含水費と比較) | ・中規模以上の工事:定期的または随時(1回~2回/日) | ||
| その他 | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | 1,000m²につき2回の割で行う。 | セメントコンクリートの路盤に適用する。 | |
| 土の 液性限界 塑性限界試験 |
JIS A 1205 | 塑性指数PI:4以下 | 観察により異常が認められたとき。 |